
(第3回までは、国立広島平和祈念館の証言ビデオでNET-GTASが翻訳した被爆者の紹介でした。今回は、特別編として、3月21日の市民・学生の集いに登場した濱恭子さんを上下2回に分けて紹介します。)
■被爆者ものがたり特別編 濱 恭子さん(89歳)の<上>

~ 大阪空襲の後、避難先の広島で被爆。今も戦争の悲惨さを語り続ける~
濱恭子さんは1925年生まれ。6歳の時に満州事変が起き、翌年には上海事変、そして12歳の時には日中戦争開始、と戦争へと向かう時代の中で幼少期を過ごした。18歳となった年には日本軍の真珠湾攻撃によりアメリカとの戦争が勃発。戦況は激化し、1945年3月13日、恭子さんの住む大阪も大規模な空襲を受けた。
後に「大阪大空襲」と呼ばれたその空襲は、274機のB29による油脂焼夷弾攻撃が行われ、大坂の街は炎に包まれた。当時、母子ふたり暮らしだった恭子さんと母は、家からとっさに持ち出したコタツ布団を何度も防火水槽の水に浸けてかぶり、降りかかる火の粉の中を逃げまどった。「生き地獄」と恭子さんは当時を語る。あまりの恐怖で頭が真っ白になり、焼け死んだ人が転がる光景を目にしても怖さや気の毒な感情はわかなかったという。
恭子さんの家も焼かれ、叔母のいる広島へ母と身を寄せた。その後、恭子さんはひとり従兄の住む島根へ疎開する。だが、広島で機銃掃射が行われるようになったと聞いた恭子さんは心配でたまらなくなり、母と祖母を迎えに行くため、広島へと向う。1945年7月のことだった。
その翌月、よく晴れた8月6日の8時15分─。青白い閃光を感じると同時に家が崩れ落ち、恭子さんは母、祖母ともにがれきの下敷きとなった。何とかはい出した3人は大阪での火の海を思い出し、直ぐにその場から逃げた。途中、「助けて」という裏の家の住人の叫び声が聞こえたが、どうすることもできなかった。
その後、恭子さんが目にした光景は大阪の空襲でも見たことのないものだった。全身黒焦げとなった丸裸の人たちが、皮をズルっとぶら下げフラフラと夢遊病者のようにあちこちから押し寄せる様子は、この世のものではなかった。
恭子さん自身もガラスが左半身に百数か所刺さる負傷をしたが、母と祖母の必死の手当てに支えられ、広島の町を逃げ歩いた。その後、雨が降り出したが、棒の上に乗せたトタン板の下で恭子さんは雨をしのいだ。棒は母と祖母が両手で支えていた。そして、その日降ったのは放射能が含まれる「黒い雨」だった。
それから9日後の8月15日に終戦の日を迎え、恭子さんの戦火に怯える時代も終わった。だが、戦後60年を機に恭子さんはかつての出来事を語り始めるようになる。その理由を「ほんとうに生き地獄だった戦争の悲惨さを皆さんにお話しして、今後どうして生きていくか考えてほしい」と語る。また、「決して戦争を望んだ訳ではないのに、戦争のるつぼにもっていかれたのです」と当時を振り返り、「戦争へと引き込まれないよう、皆で力をあわせないといけない」と訴える。その思いは海を越えたフランスでも語られ、国境を越えた共感と連帯を生んだ。<つづく>
(榊原 恵美子 =職員)



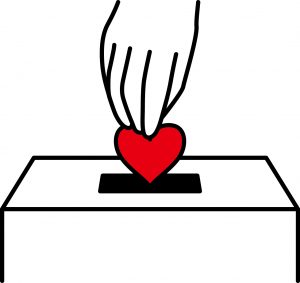










コメントを書く